1 初めて無罪を争った刑事事件
今後誰かの刑事事件で役立てばよいという気持ちを持って、自分が担当した刑事事件の反省と今後同じ事件を担当する際の改善点をまとめてみました。こうした内容は一般の人には使いどころが難しい知識です。というのも、刑事事件では、同じ罪名でも個別具体的な事案に即して考える必要があるからです。そのため、同業者向けの内容となりますが、何かの参考になればと思っています。
2 事実の概要
マンションの共用部である廊下にて、同場所に設置されていた消火器(家庭用のABC粉末消火器)を噴射して、共用部である廊下の床、壁、各部屋の玄関扉を消火剤を付着させ、汚損した。
3 被疑事実
建造物損壊罪(刑法260条)
刑法260条「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」
4 争点
消火器を噴射して、共用部である廊下等に消火剤を付着させ、汚損した行為が建造物損壊罪での「損壊した」に該当するか否か
争点が生じた理由
軽犯罪法1条33号では、「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者」と規定されている。「これらの工作物」には「他人の家屋」が含まれるところ、犯行現場となったマンションも「他人の家屋」に該当する。そのため、マンションを汚したという場合には、軽犯罪法1条33号が成立する(刑法の建造物損壊罪は成立しない)と評価できるからである。
なお、軽犯罪法について参考となる書籍として伊藤榮樹原著・勝丸充啓改訂『軽犯罪法(新装第2版)』(立花書房・2024年)がある。
5 判決内容(概要)
ABC粉末の消火器に内蔵されている消火剤(ABC粉末)は目に入ったり、粘膜に付着すると危険なものだと、消火器の説明書に記載がある。
その危険な薬品が共用部分の廊下等に強く付着していた。
そのため、共用部分の廊下はマンションの住民が行き交う場所であり、そこに危険な薬品である消火剤が付着している状態は行き交う住民にとって危険な状態だった。
すると、マンションという建造物の効用を害する状態に達していたと評価でき、「建造物」を「損壊した」と評価できる。
よって、建造物損壊罪は成立する。
反省
汚損対象の特定を明確に特定しきれなかったこと
起訴状では、消火剤が付着した部分について、「廊下等」というような記載でまとめられていた。修習でも起訴状の「等」は必ず釈明しようと教わるため、この事案でも「等」を明らかにするように要請した。付着した部分によって建造物に与える影響が異なるため、消火剤が付着した部分を特定することは防御上、不可欠であった。
そして、公判で検察官による口頭で回答があったが、明確に特定できていない回答があったのみだった。そして、私も「そんなものか」と引いてしまった。書面で回答するようにその場で要請するべきだった。なお、当時、「等」を明らかにするように要請したことで満足したことが原因であり、判決文でも、消火剤が付着した部分は不明瞭なままだった。
汚損したことをどのように評価して「損壊した」と結論づけたのかを明らかにしなかったこと
今回の事件での起訴状では「共用部である廊下を汚損した」ことが「建造物」を「損壊した」と評価されていた。こうした建造物を汚損した場合に有名な判例として、公園便所にスプレーで落書きした事件(最決平成18年1月17日刑集60巻1号29頁)がある。この事件では、建造物を汚損させた程度が「外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせた」と評価できれば、建造物を損壊したと評価できるとした。
そのため、私の頭の中では、消火剤が建造物に付着したことが「外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせた」に該当するかが争点であると納得してしまった。結果として、この判断は早合点だった。
ただ、前述のとおり、裁判官は、廊下等の外観を汚損したとは評価せずに、廊下を行き交う人の通行が妨げられる状態だったことを指摘して、その点で物の効用を害した(損壊した)と評価した。
すると、弁護人として、結果として、攻撃の対象となるポイントを外していたこととなり、致命的な齟齬が生じる結果となってしまった。
そのため、弁護人として、検察官が建造物をどのように「損壊した」と評価したのかを最初の時点で明らかにして、争点をもっと明確に特定して、検察官、弁護人、裁判官とで具体的な争点を共有するべきだった。
なお、推測であるが、判決が出るまでは検察官も「消火剤が住民の身体に危険な薬品で、このせいで住民の通行が妨げられる状態だった」とは考えていなかったと思われる。なぜなら、検察官の論告では、「細かい消火剤が降り積もっており、この状態で通行すれば滑る可能性があった」(これを裏付ける証拠の提出はない)と「通行する人の衣服や靴に消火剤が付着して所持品がその都度汚損する状態だった」(これを裏付ける証拠の提出はない)という点の指摘があっただけだからである。当初から考えていたのであれば、証拠を提出していただろう。
もし同じような事件を再度担当することになった場合の対応について
①第1回期日で消火剤が付着した部分を明確に特定させる。
②第1回期日で消火剤が付着したことがどう「損壊した」と評価できるのかを特定させる。
→ただし、検察官から「その点は論告で明らかにする」と言われてしまう可能性があるが、その際には「争点を明確にするためにも今の時点で回答する必要があること(起訴したんやから、その点は既に結論づけてるやろ、検察庁内の決裁経た上での起訴やろ)」と粘る必要がある。
③マンション内の住民の通行が妨げられた事実があるのか否かを明らかにする。
→例えば、廊下の通行が実際に禁止されていたのか、消火剤が付着したことでマンション住民に健康被害がでたのか、現場を鑑識した警察官が完全防備の上で鑑識を実施したのか、警察官からマンションの住民等に対して通行しないように指示・指導があったのか、、、という点である。
④消火剤の説明書の証拠意見について「不同意」だと回答する。
→消火剤の危険性について、証人尋問をやったとしても争う必要がある。
感想
裁判官の判決を聞いたときの感想としては、「そこを争点に思っていたなら、指摘するべきではないか。検察官も弁護人もその点についてまったく攻撃防御できていないぞ。今回のマンション内で消火剤が付着した部分の通行を禁止した事実もなければ、警察がそれを指導した事実もない。誰も消火剤があるから、通行をしてはいけないと言った形跡はないぞ。裁判官が指摘する危険は抽象的な危険ではないか。消火器を使った消火活動は建造物損壊罪の構成要件に該当した上で、正当行為(刑法35条)として違法性阻却されると考えるのか。」などと思っていました。また、「民事訴訟だと、弁論主義に違反してるやろ」とも思っていました。
ただ、反省点として、裁判官を分からせることができなかったという点は弁護人の責任だと思っていました。また、「裁判官なら分かるだろう(私の言いたいことを分かってくれるだろう)」という甘い認識が当時の私にあったのだと、今でも本当に情けない気持ちと自分に対する怒りがわいてしまいます。
今の刑事裁判で無罪を主張する場合には、「無罪だと裁判官に分からせる」という気概が重要だと思っています。「裁判官なら分かってくれる」「なんとか裁判官に分かってもらう」という気概では、どこかでの対応に甘さがでてしまいますし、それが通じるほど刑事事件は甘くない状況です。そのためには、公判において、検察官や裁判官との訴訟指揮に真っ向から対立することも厭わないべきです。だって、彼らに譲歩しても、基本的に我々に有利なことはしてくれないですし。そんなに甘くない。
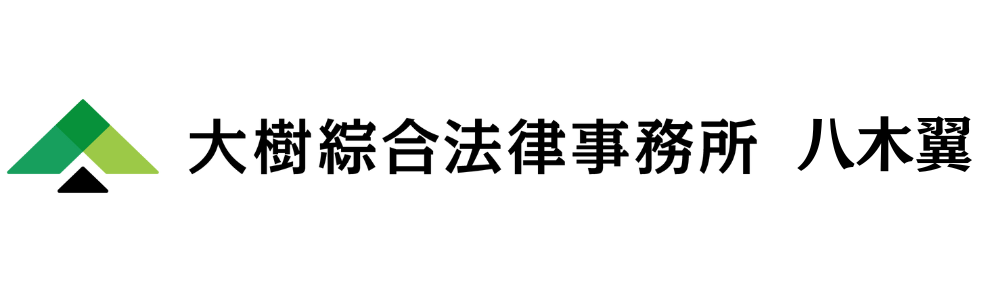


コメント