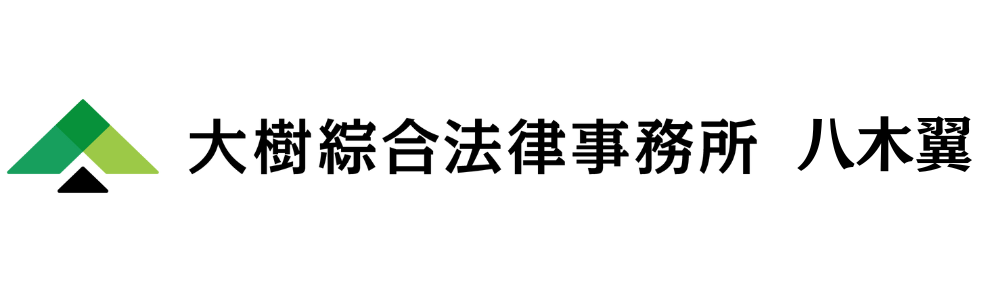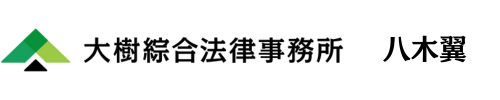私がこれまで弁護士として多くの事件に対応してきました。ここでは、私が取り扱ってきた4つの分野について紹介いたします。
① 刑事事件
刑事事件では、任意捜査が始まる前から起訴後の裁判(控訴審も含む)での対応まで、さまざまなケースに関わってきました。
【対応事例】
- 突然の逮捕により不安を抱えるご家族からのご依頼で、早期の釈放に向けた活動を行い、勾留請求が却下され、早期の身柄解放が実現したケース
- 示談交渉により、不起訴処分を獲得し、前科を回避できたケース
刑事事件は、スピーディーな対応がなによりも重要です。状況に応じた最善の対応を心がけています。
依頼のキッカケ
依頼者は、実家で両親と同居していた男性で、金銭的には余裕があるものの、窃盗をどうしてもしていまうという人でした。その人は、過去に執行猶予付きの実刑判決をもらったものの、その後も窃盗を繰り返してしまい、複数の被害店舗から被害届が出されて、最終的には警察に逮捕されました。その段階で、その男性の家族から依頼があり、私が担当することになりました。
解決のストーリー
依頼を受けてすぐに、男性がいる警察署にすぐに行き、その男性と話をしました。窃盗の事実を確認すると、間違いなく自分がやったとの回答でした。その旨を心配している家族に共有した方がよいかと男性に尋ねると、「お願いします」との回答もありました。
そこで、男性の家族に対して、男性の状況や犯行の自白の件を報告しました。男性の家族からは「すぐに警察署から出してほしい」という要望があり、男性も「ここから出たい」と希望したため、外に出られるように対応しました。
具体的には、検察官と交渉をしたものの、勾留請求がなされ、男性に勾留決定がでたため、勾留決定に対する不服申し立てを行いました。本人の反省文、被害店舗に近づかないという誓約書や同居家族の身元保証書等を添付し、なんとか外に出られることになりました。
身柄解放されたものの、刑事事件は終わりではありません。本人と同居家族と一緒に今後の対応方針を協議しました。本人らの強い希望は「刑務所には行かずに、更生したい。」というものでした。ただ、私の見立ては、「執行猶予期間中の犯行だから、被害店舗と示談をしても、起訴の可能性や実刑の可能性は高い。」というものでした。
そのため、本人らには「刑務所に行く覚悟を持ってもらいつつも、示談等の対応を進め、刑務所に行かなくするように対応しましょう」と説明をしました。
ただし、被害店舗との示談だけでは再度の執行猶予を狙うことは非常に難しいと思いました。というのも、前回の窃盗の刑事裁判でも同じように被害店舗と示談等をして、反省の態度を示していたからです。前回と同様の状況を説明しても、裁判所が再度の執行猶予をくれる可能性は低いです。
そこで、更なる方針として「家族だけのサポートだけでなく、もっと周囲のサポートを受けるように体制をつくる」ということを提案しました。
具体的には、窃盗に関する依存症の可能性があったため、依存症に関する病院を受診してもらい、そこでの更生プログラムを作ってもらいました。
なお、本人は病院に行くことに抵抗があり、「自分は病気ではないから、行く必要はない。」と強く言っていました。ただ、家族の説得や私の「1回受診して、医師の意見も聞いてみましょう。異常がないことを確認することも大事ですよ。また、病気だとわかっても、治療という方向性が分かりますよ。」という説得で受診を決意してくれた経緯があります。
最終的に、男性は窃盗が理由で刑事裁判を受けることになりましたが、その裁判の中で、被害店舗との示談成立、本人の更生の医師、周囲のサポートを受ける体制があること、医師の更生プログラムを実際に受けていること等を主張して、再度の執行猶予を得ることができました。
感想
執行猶予期間中に犯罪を行った場合、再度の執行猶予を得ることは本当に難しいです。難しい理由は、本人が警察署等に勾留され、外部との交流が遮断される結果、周囲のサポートを十分に受けることができなかったり、その体制作りができない点です。
今回男性が外に出られなかったとすると、病院に受診することはできず、医師の更生プログラムの内容や実施状況を裁判所で主張することは難しかったように思います。
また、本人が病院を受診してくれたことも非常に良かったです。ただ、病院を受診してもらうことは決して容易ではありません。まずは本人に「自分は病気だ。だから、病院に行く必要がある。」と認識してもらう必要があるからです。そう認識してもらうことは非常に難しいです。誰も「自分は病気だ」と思いたくないですから。
そして、今回のケースでも、ご本人の説得にとても苦労しました。ただ、結果論ではありますが、本人からは「医師の意見を聞き、何をすればよいかの方向性が分かったときは心が軽くなった。物を盗むことをやめたいと思いつつも、自分だけでは辞められなくて辛かった。」という言葉を聞きました。
最後に、被害店舗との示談も苦労しました。最近の店舗は、示談に応じてくれないことが多いからです。何度か足を運んでお話を聞いていただき、「許すつもりはないが、弁償金は受領する」と言っていただくことができ、本人の店舗への立ち入り禁止を条件に示談に応じてもらいました。
依頼のキッカケ
依頼者は、酔っ払うと粗暴になってしまう特徴をもつ独身男性でした。今回、その男性が店舗で飲酒していたところ泥酔してしまい、同じ店舗にいた男性と口論になって殴ってしまいました。被害者は警察に被害届を出したものの、依頼者は逮捕等はされませんでした。ただ、依頼者は何度か警察署に呼ばれて任意で事情を説明していました。
傷害事件の場合、被害者と示談をすることが解決に有用なのですが、被害者は「加害者との示談を希望していない。本人からの連絡には応じない。」と頑なだったようです。
そこで、依頼者が「弁護士を付ければ、被害者と示談できるかも」と思い、被害者との示談交渉という内容で私に依頼がありました。
解決のストーリ
私が被害者に初めて連絡をとったとき、被害者からは「本人と関わりたくないし、示談もしない。刑務所に行けばいい。」という言葉がありました。被害者としての感情としては当たり前だと思いました。
そこで、私は、依頼者に対して、被害者の発言をそのまま伝えました。それと同じタイミングで、依頼者に前科はなく、暴行の程度も比較的軽微だったので、「罰金はあり得るが、刑務所に行く(実刑判決がでる)という結果はなかなか難しい事案だから、無理に示談をしなくてもいいかもしれない」とも提案しました。
しかし、依頼者は「自分のやったことなので、しっかりと謝りたいし、償いたい。だから、被害者と示談できるように尽力してほしい」という要望を受けました。
そこで、依頼者も逮捕されておらず、時間的に余裕があったので、被害者に対して接触を取り続けて、示談をする方向で対応することにしました。具体的には、依頼者に反省文や反省の弁を伝える手紙を何度か作ってもらい、また慰謝料の積み立てもしてもらいました。
そして、私から被害者に対して「直接会ってお話できる時間を作っていただけないか」と根気強くお願いしました。
すると、被害者の方から「一度だけなら、会ってもよい」という返事があり、無事に会うことができました。
被害者と会った際には、時間を取っていただいたことに感謝を述べ、怪我の様子や治療の内容、いまの気持ち等を聞きました。大体2時間ぐらい話を聞いた上で、依頼者のいまの気持ち等を聞いてもらえないかとお願いしました。
そして、被害者の人からの了承を得た上で、本人が反省していることや手紙等を作成したこと、慰謝料の積み立てをしており、示談をしていただけないかとお願いをしました。被害者からは「示談をすると、依頼者は刑事処分を受けないのではないか」という質問があり、「刑事処分は最終的には検察官が決めるので、私の方で確実なことは言えません。ただ、今回の示談が依頼者に有利に扱われることは間違いないと思います。」と回答しました。結局、その日に示談に関する被害者の意向は聞けませんでした。
しかし、後日、被害者が警察と相談したようで、警察からも示談をして被害弁償を受けた方がよいと言われたようで、被害者の気持ちの整理がつき、無事に示談ができました。
そして、示談の結果を警察に報告して、無事に依頼者は不起訴処分になりました。
感想
刑事処分において被害者との示談が依頼者にとって有利に働くことは多いです。特に、暴行事件や傷害事件等では被害者との示談の有無によって刑事処分が大きく変わるケースもあります。
ただし、被害者との示談は想像以上に難しい場合があります。例えば、依頼者が逮捕・勾留されている場合、検察官が刑事処分を判断するまで時間は、逮捕・勾留されていない場合と比較して、非常に短いです。ときには、示談交渉に使える時間が一週間もない場合もあったりします。
今回のケースでは、依頼者が逮捕・勾留されていない場合だったので、交渉に使える時間は比較的長くありました。そのため、被害者との示談が成立したと思っています。なので、もし依頼者が逮捕・勾留されていたら、示談成立は難しいタイプの被害者だったといえます。
そして、示談を嫌がる被害者は多くいらっしゃいますが、それは当然だと思います。加害者に刑事処分等の罰を受けてほしいと思うことは当然ですし、それにマイナスに作用する「示談」をすることに抵抗を示すことは当たり前です。
ただし、そういった場合でも諦めずに工夫しながら示談交渉をすることが大事だと思います。
今回のケースだと、被害者の人の話をしっかりと聞きました。その上で、被害者の許可をとったうえで、依頼者の話をしました。それぐらいに気を遣う必要があると考えていました。
今回のケースでは被害者との示談が成立しましたが、被害者との示談が成立しない場合も多くあります。加害者の反省や謝罪の言葉を聞きたくないと一切を拒絶する被害者の方も多くいらっしゃいます。
今回の依頼者にも「あなたの反省の気持ちは私には十分に伝わっています。ただ、あなたが反省しているからと言って、被害者があなたの話を聞く義務はありませんので、どうして許してくれないのかと焦ってはいけません。焦らずに対応していきましょう。」と説明をして、対応を続けました。
依頼のキッカケ
依頼者は会社員で副業ブームに乗っかり、副業を始めていました。ただ、その副業の内容が「詐欺」だと明確に言えないまでも、「詐欺」かもしれないと疑わしい事業内容でした。実際、複数の人が警察に相談に行くなどしており、真っ当な事業内容だとは断定しにくいものでした。
もちろん依頼者自身は、詐欺だとは思わずに、そのまま副業を進めていたのですが、被害者から「被害届を出した」という連絡があり、実際に捜査機関から「話が聞きたい」という連絡があったことから、あわてて弁護士を探したようでした。そこで、私に刑事弁護の件で依頼がありました。
解決のストーリー
まず、事業内容をしっかりと聞くと、「詐欺ですね」と明確に言えないまでも、「詐欺ではないしょう」と強く言えない事情のある事業内容でした。ただし、依頼者に顧客を騙す認識はなかったことや依頼者の「こんなことになったので、事業をやめたい」という希望があったため、顧客全員への返金対応を進めながら、捜査機関へは「事業が詐欺ではない」と説明していくことになりました。
まず、顧客に対しては、依頼者と相談しながら返金対応の案内文を作成して、返金対応の連絡を取り、返金対応を取りました。驚くことに事業を続けてほしいという声も一部の顧客からあったようです。ただ、そこは依頼者から事情を説明して、諦めていただきました。
他方で、捜査機関への対応については、捜査機関の担当者と連絡を取り、「本人に真摯に対応させます」と言った上で資料開示の要望があった場合や背景事情を説明する際には弁護士も一緒に対応しますと言いました。そして、実際に、本人が捜査機関に言った際には、取り調べに立ち会うことはできませんでしたが、担当者と本人、私の3人で話をする場面も設定してもらいました。そして、私の方から事情説明という形で報告書を提出しました。
その後、何度か本人からの聞き取りが行われましたが、事件性なしということで刑事処分を受けることはありませんでした。
感想
詐欺事件では、事業等の取引内容に対して警察官がどこまで理解できるかが問題になると思っています。つまりは、事業等の取引内容が誤解されると、その誤解のまま捜査機関の内部で意見ができ上がってしまうということです。そうなると、予期せぬ結果を導くことになってしまいます。
ときおり、捜査機関に対して「ちゃんと話をすれば、理解してくれる。」と思っている依頼者がいますが、私の経験上、「しっかり説明したつもりになっているだけで、しっかりと伝わっていない。」と思うことがとても多いです。
今回のケースでも、依頼者の方から初回相談の際に「詐欺ではないから、警察も分かってくれるでしょ」という発言があったので、「分かってくれない場合には致命的なリスクを負うから、一緒に対応した方がいいかもしれませんね」と提案しました。
そして、捜査機関担当者と本人、私との3人での話し合いの場面では、本人の「危ない説明」(誤解される説明)がいくつかあったので、その場で訂正し、資料を見せながら実態をしっかりと説明することができました。正直なところ、捜査機関の担当者が弁護士と話をしてくれる機会はあまりないため、非常に助かった場面でした。
最後に、顧客に返金した上で事業を全て終わらせたことも事件性がないという判断につながった可能性もあるところです。
ただし、今でも今回の依頼者の事業が「詐欺」だったかと言われると、「グレー」としか言いようがないと思っています。
事業を起こす際に弁護士の意見を聞くことは大事だと思いますが、「グレーな場合でも事業を進めるか」という最終的な判断は本人にしてもらう必要があります。ただ、その判断の際には、リスクを踏まえて行う必要があるので、やはり、弁護士に一度相談してほしいところです。
依頼のキッカケ
これは、国選弁護人として、被疑者が逮捕された段階から対応していた事件になります。被疑者は、素行がよろしくないグループに属していた人で、仲間内での喧嘩が傷害事件に発展していったものでした。
解決のストーリー
被疑者には前科があり、その他の事情もあいまって、傷害事件といえども、起訴されれば、実刑判決を受ける可能性がそれなりにあるケースでした。
そこで、検察官に起訴を諦めさせるように対応したいと考え、そのために、被害者が刑事裁判に協力しない旨を条件として示談締結を目指すこととしました。というのも、刑事裁判を進める上で被害者の供述は絶対に必須であるところ、その被害者の協力を得られないように進められれば、、、と考えました。
実際に被害者と示談交渉をしたところ、被害者本人は刑事裁判に協力しない旨での示談成立に消極的でしたが、接触禁止条項等の内容を説明したり、金額を説明したりして、被害者の納得を得ました。
そして、無事に示談が成立し、示談書を検察官に提出したところ、処分保留で釈放となりました。
感想
刑事裁判に協力しない旨の条項付きで示談をすることは初めての経験だったので、成功する可能性は未知数でした。被害者がどう反応するか想像できなかったので、出たとこ勝負でした。
そのため、示談交渉の際には、被害者からの質問には誠実に回答して、じっくりと考えてもらおうと思って対応をしました。誠実な対応は交渉の基本です。実際、被害者から「この条項を結んで、実際に刑事裁判で証人として対応したときにはどうなりますか?」と質問されたので、「刑事裁判で証言したことについて、法的な責任を問うことは難しいと考えています。本人にもそのように説明しています。ただ、お金をもらったのに、約束を破ったという事実が残ります。」と説明しました。
被害者の証言以外の証拠があった場合には、検察官も「別の証拠で立証しよう」と思うので、今回の条項はあまり効果的ではないかな、、と思うところです。
② 交通事故
交通事故では、主に被害者側側の立場からのご相談に対応してきました。
【対応事例】
- 保険会社からの提示額が適正かどうか不安に感じた被害者の方のご相談で、示談交渉を行い、慰謝料が2倍以上に増額されたケース
- 後遺障害の認定が難しいとされていたご相談で、医師と連携しながら適切な資料を提出し、後遺障害等級の認定を受けられたケース
交通事故は、保険会社との交渉が複雑になりやすいため、被害者の正当な権利が守られるようサポートしています。
交通事故対応に関する詳細は次の記事をご覧ください。
③ 労働事件・企業法務
労働問題では、労働者からのご相談だけでなく、企業側のご依頼にも対応し、双方の立場を理解した解決策を提案してきました。
【対応事例】
- 不当解雇に悩む労働者の方のご相談で、交渉の結果、解雇撤回と職場復帰が実現したケース
- 残業代の未払いに関するトラブルで、証拠の整理と交渉を行い、本来受け取るべき賃金が支払われたケース
- 問題行動のある社員に対して苦慮していた企業側からの相談で、対応方針や具体的な対応方法を協議・サポートしたケース
労働事件では、労働者も企業も証拠の確保が重要です。事実関係をしっかり整理し、依頼者の権利が守られるよう全力でサポートしています。
依頼のキッカケ
もともとサービス残業が非常に多かった会社を退職した依頼者が、退職してから休みつつ体調を戻し、サービス分の賃金を請求したい、、、と思い、弊所にご相談されたことがきっかけです。
解決のストーリ
依頼者は、退職前に自分のタイムカードをデータできっちりと残されている方でした。また、業務内容やタイムカードの設置状況や運用状況を聞き取り、タイムカードに記載された時間が労働時間だと十分に推測できると判断できました。
そこで、依頼者から事情等を十分に聞き取り、元勤務先に対して、残業代を請求したいので、依頼者の労働条件や労働時間に関する資料を開示してほしいと連絡しました。会社側も、抵抗することなく、すんなりと労働条件や労働時間に関する資料を開示してくれましたし、開示された資料も依頼者が持っていた資料と一致していたので、資料の偽造等を追及することなく、検討ができました。
ただし、そこから先は泥沼でした。相手方企業は、残業は許可制で、依頼者は許可をとっていなかったので、残業代は発生しないと強く主張してきました。依頼者の話によると、許可制が採用されていたものの、その制度が形骸化している事情が多々あったため、当方も「その許可制は有効ではない」と反論をしました。
しかしながら、交渉での合意には至らず、平行線をたどったため、労働審判を申し立てることとなりました。
労働審判でも、相手方企業は、「許可のない残業について、残業代を支払うことはできない」と強く主張していました。しかし、労働審判の初回期日で、依頼者から事情が聞き取られ、依頼者の元上司の聞き取られると、労働審判員から「許可制が採用されているが、運用がこれでは、、、許可制が有効だというのは難しいと思う」との発言がありました。
そこで、労働審判の2回目の期日で、労働審判委員会から和解案の提案があり、双方が納得し、調停が成立して、解決しました。そして、後日m無事に残業代が払われました。
感想
このケースで、残業の許可制を採用しているものの、その運用がしっかりとされていなかったという事情がありました。例えば、許可申請書の提出は原則として残業する前とされていながら、実態は残業後に提出されることが横行していたり、相手方企業がタイムカードで無許可の残業を確認しながらも、従業員に対して何らの指導もしていないなどの事情がありました。
そのため、交渉の段階から「いや、この運用実態で許可制は難しいですよ。」と回答していましたが、相手方企業の納得を得られず、労働審判を申し立てることとなりました。相手方弁護士の苦労も透けて見えていたので、「向こうは向こうで大変そうだ」と思っていました。
④不動産事件(オーナー側及び賃借側)
不動産問題では、依頼者の状況に応じた最適な解決方法を提案し、対応を進めてまいりました。
【対応事例】
- 所有している賃貸物件を取り壊す際の賃借人の任意の退去を促す交渉対応
- 所有している賃貸物件で賃料未払いがある場合の退去及び賃料回収の訴訟対応
- 賃料滞納者の代理人として家主と契約継続のための交渉対応
不動産事件はスピード対応が損害を最小限にする最も大切な対応です。
まとめ
これまでに、次のようなご相談を数多く取り扱ってきました。
✅ 刑事事件:身柄の早期解放、不起訴処分の獲得など
✅ 交通事故:保険会社対応、損害賠償の増額、後遺障害等級認定のサポート
✅ 労働事件:不当解雇や未払い賃金の対応、問題社員の企業側対応
✅ 不動産事件:立ち退き交渉、未払賃料回収、未払賃料対応
どのような問題でも、「相談してよかった」と思っていただける解決策を目指しています。
「この悩みは弁護士に相談してもいいのかな…」と迷われたら、どうぞお気軽にご相談ください。また、ここでご紹介した事件には分類できない事件も多く取り扱ってきました。お話を伺い、最善の道を一緒に考えてまいります。