1. 在宅捜査では「国選弁護人」がつかない
最大のポイントは、在宅捜査の場合は国選弁護人がつかないことです。
逮捕・勾留された場合は、資力要件を満たせば国選弁護人が選任されます。しかし、在宅捜査では逮捕・勾留されていないため、たとえ被疑者であっても国選弁護制度の対象になりません。
そのため、逮捕・勾留されずに刑事手続きが進む在宅捜査では、弁護士に一度も相談することなく、手続きが進んでしまうリスクがあります。
2. 取調べへの対応が重要
在宅捜査でも警察や検察の取調べを受けることがあります。
このときに適切な対応をしないと、不利な供述をしてしまうリスクがあるため、事前に弁護士と相談し、取調べに備えることが重要です。具体的には、自分が捜査機関にこれから話すことにどのような意味(リスク)を持っているかを知るべきだということです。
刑事手続きは被疑者自身のために進んでいく手続きで、被疑者がその結果の責任を負います。そのため、その刑事手続きの中での被疑者自身の振舞いがどのような意味(リスク)を持つかを知って、どのような振舞いをするかを選択するべきです。
3. 不起訴処分を目指せる
在宅捜査の場合、検察が「起訴するかどうか」を判断するまでに時間を要します。これは、逮捕・勾留された場合よりも比較的に長い時間を要します。
そのため、逮捕・勾留された場合よりも弁護士が被疑者のために対応できる時間が比較的多くとれますので、不起訴処分(=前科がつかない)になる可能性もあるということです。
弁護士に依頼すれば、検察への意見書の提出や被害者との示談交渉などを通じて、不起訴に向けた弁護活動をします。
まとめ
在宅捜査は逮捕・勾留されていないからといって軽視できるものではありません。
特に、在宅捜査の場合、国選弁護人がつかないため、弁護士のサポートを受けるには自分で依頼する必要があります。
弁護士に相談することで、不起訴の可能性を高めたり、取調べへの適切な対応を学んだりすることができ、結果的に今後の人生への影響を最小限に抑えることにつながります。
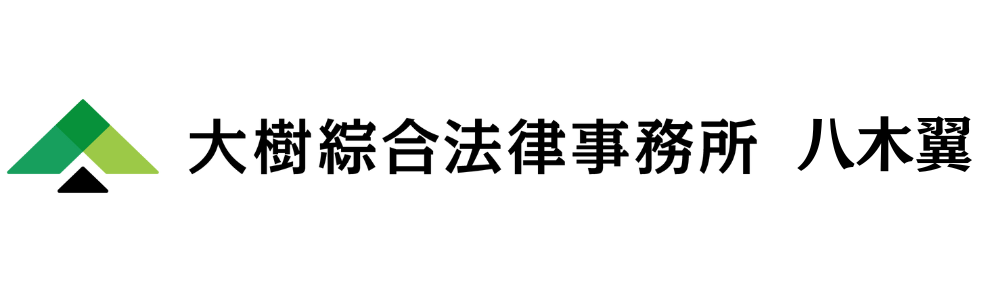


コメント